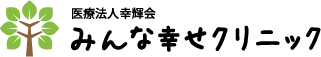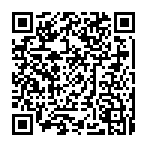【喘息とは?原因・検査・治療法をぱっと解説】
「夜になると咳が止まらない」「運動するとゼーゼー息苦しい」――そんな症状があるとき、もしかすると喘息かもしれません。
喘息は、子どもから大人まで誰でも発症しうる病気で、放っておくと生活の質を大きく下げてしまいます。
今回は、喘息の症状・原因・検査・治療法までを、患者さんにもわかりやすく解説します。
喘息とは?どんな病気?
喘息は、気管支に炎症が起こり、気道が狭くなることで呼吸がしにくくなる病気です。
発作的に呼吸困難を起こすこともあれば、慢性的に息苦しさが続く場合もあります。
ここではまず、典型的な症状と、その仕組みをみていきましょう。
喘息の症状
- 咳(特に夜間や早朝に出やすい)
- 息苦しさ(呼吸困難)
- ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音
- 季節や運動、ストレス、風邪などで悪化
軽い咳だけで済む方もいれば、救急搬送が必要になるほど重くなる方もいます。
「咳が長引くな」「夜に苦しくなることが多いな」と思ったら、早めに医療機関で相談してください。
喘息のしくみ
喘息の背景には「気道の炎症」があります。
- 気管支の粘膜が炎症で腫れる
- 気道が狭くなる
- 粘液が増えて空気の通り道がふさがる
この結果、呼吸がしにくくなり、咳やゼーゼー音が出てしまいます。
炎症は、アレルギー反応や大気汚染・煙などの刺激物によって悪化します。
喘息の原因を探る:アレルギーとの関係
喘息の多くはアレルギーと関係しています。ただし、遺伝や環境要因も関わるため、複合的な要因が発症につながります。
アレルギー物質との関連性
喘息を引き起こしやすいアレルゲン(原因物質)は次の通りです。
- ハウスダスト・ダニ
- 花粉
- ペットの毛
- カビ
これらを吸い込むことで気管支に炎症が起こり、発作が誘発されます。
自分にとってどのアレルゲンが強く影響しているかを特定することが、予防の第一歩です。
遺伝的要素と環境要因
- 家族に喘息やアトピー性皮膚炎がある場合、発症リスクが高まります
- ただし遺伝だけでは決まらず、環境要因も大きく関与します
代表的な環境要因は、
- 大気汚染
- たばこの煙
- ウイルス感染
これらを避ける工夫が、喘息の発症・悪化防止につながります。
喘息の検査方法:診断のためのステップ
「咳が長引く=喘息」とは限りません。診断には、いくつかの検査が必要です。
問診と身体診察
医師は、症状の経過や生活習慣を詳しく聞き取り、聴診器で呼吸音を確認します。
- 咳や呼吸困難の頻度
- いつ症状が強くなるか
- 改善する条件はあるか
これらをもとに、喘息の可能性を判断します。
肺機能検査(スパイロメトリー)
息を吸ったり吐いたりする力を測定する検査です。
気道の狭さを客観的に評価することができます。
アレルギー検査
血液検査や皮膚テストで、アレルゲンを特定します。
- 血液検査:IgE抗体の測定
- 皮膚テスト:アレルゲンを少量投与し反応を見る
原因物質を知ることで、発作予防の対策をとりやすくなります。
喘息の治療法:薬物療法と生活習慣の改善
喘息は「完全に治る」病気ではありませんが、適切な治療でコントロールすることができます。
吸入薬の種類と使い方
治療の基本は「吸入薬」です。
- 気管支拡張薬:気道を広げて呼吸を楽にする
- 吸入ステロイド薬:炎症を抑えて発作を防ぐ
正しい使い方がとても大切です。使用方法に迷ったら、医師・薬剤師に確認しましょう。
生活習慣の改善:発作予防のためのポイント
薬とあわせて、生活習慣の工夫も大事になってきます。
- 室内のハウスダスト・ダニ対策
- 花粉シーズンは外出や換気に注意
- ペットとの接触を控える
- 禁煙(受動喫煙も避ける)
- 規則正しい生活とストレスケア
こうした積み重ねが、発作予防と生活の質の改善につながります。
【まとめ】
喘息は「うまく付き合うことができる病気」です。
- 咳や息苦しさが続くときは早めに受診
- 検査で原因や重症度をしっかり確認
- 薬物療法+生活習慣の工夫で発作を予防
自分に合った治療法を見つけ、無理なく続けることが大切です。
「治療を始めれば、普通の生活ができる」のです。

https://www.allergy-i.jp/zensoku/kihon/about/
喘鳴(ぜんめい)の症状と病気 – 大阪市西区 西大橋・本町・心斎橋・四ツ橋の内科・呼吸器内科・循環器内科 みんな幸せクリニック